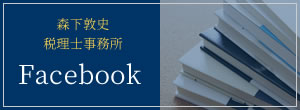遺言書の種類とは?3つの種類と内容について詳しく解説
遺言書は、遺産相続において故人の意思を反映するための重要な手段です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、遺言書の3つ「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について詳しく解説します。
遺言書の種類について
遺言書は、財産をどのように分配するのか、誰に何を承継させるのかという意思を明確にするための重要な書類です。
遺言書がない場合は、相続は民法の規定に従うことになります。
そのため、遺言者本人の意思を反映させるには遺言書の作成が必要です。
遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれについて詳しく説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです。
遺言者本人が手書きで全文を書く必要があり、パソコンで作成したものや録音・録画、代筆などは無効となります。
ただし、相続財産の目録については、手書きでなくパソコンで作成することが可能です。
遺言書には正確な日付を記載し、氏名をフルネームで記入する必要があります。
複数の遺言書が存在する場合は、有効となるものは、新しい日付のものになります。。
遺言書の有効性には、署名と押印が必要であり、印影がはっきりしていることが求められます。
印鑑の種類は100均などで売られている認印でも法的に問題ありませんが、遺言者本人が書いたことの有効性を示すためには、実印を利用した方が良いといえます。
自筆証書遺言のメリットとして、費用がかからず手軽に作成でき、内容を秘密にできる点が挙げられます。
一方で、法的に無効な内容であったり、遺言内容が曖昧であることによる相続人同士で争いになったりというリスクがあります。形式不備による無効になる可能性があったり、なお、自宅で遺言書を保管する場合、紛失や変造などのトラブルが考えられますが、法務局保管制度を利用することでリスクを回避することができます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成してもらう遺言書のことを指します。
遺言者の希望する内容を公証人という長年法律関連で働いてきた者が作成してくれること、また作成する際、証人2人がいるため法的に無効となるリスクがほとんどありません。
また、公証役場で保管されるため、紛失や隠匿の心配がないことは、公正証書遺言の大きなメリットと言って良いでしょう。
公正証書遺言のデメリットとしては、作成に費用がかかることや、証人2人の手配が必要であることが挙げられます。
費用については遺産の価額が高くなるほど手数料が高くなる傾向にあります。
証人自体は公証人に用意してもらえることも可能ですが、通常料金に上乗せして、証人の用意した費用も支払う必要があります。
なお、公証人は法律的に有効な形で遺言を作成しますが、具体的な相続相談には応じられません。
誰にどのような財産を残したいのかなど個別具体的な相談を行いたい方は弁護士などの専門家に相談することを検討する必要があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証役場で証明してもらう方法です。
封を施した遺言書を公証役場に提出し、公証人がその存在を証明します。
遺言内容を秘密にしながら偽造・変造を防ぐことができます。
秘密証書遺言のメリットは、遺言内容を他人に知られずに済む点です。
また、署名押印が遺言者本人であれば、様式に制約はありません。
封印した遺言書を公証人に提出し、証人2名以上の立会いのもとで、遺言者の氏名・住所を申述し、公証人が日付と申述内容を封筒に記載し、署名捺印します。
封筒内の遺言書は、氏名以外は代筆やパソコン作成も可能です。
ただし、法的不備があると無効になるリスクや、検認が必要となる点がデメリットです。
さらに、検認時に封印が解かれていた場合は無効となり、保管場所は自宅のみとなるため注意が必要です。
まとめ
今回は遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴を踏まえ、遺言者の希望に合った方法を選択することが大切です。
遺言書を作成する理由として、ご自身の死後相続人同士で争ってほしくないということがあると思います。
しかし、遺言内容が曖昧だったり、1人の相続人だけが突出して得するような内容を残すと、かえって争いになる可能性が高くなります。
そのため、遺言書を残したい場合には弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【個人事業主の確定申...
個人事業主の悩みの一つとして上がるものとして代表的なものは税金の問題、とりわけ確定申告ではないでしょうか。確定 […]

-
確定申告の流れ
確定申告は、個人事業主や個人が、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、税務署に確定した所得税額を申 […]

-
定款の重要性とは? ...
「定款」は、会社を設立するために必ず作成しないといけない、会社の根本原則です。設立後もこれをなくす […]

-
中小企業庁の新事業進...
新型コロナの影響や社会情勢の変化により、経営の継続が難しくなっている企業の挑戦を後押しするのが、中 […]

-
年末調整の対象になる...
勤め先から支払われる給与は、予測される所得税等の納付分を考慮して天引きがなされています。しかし年末 […]

-
法人企業の税務調査の...
税務調査は税務署が公平な課税を行うために、帳簿などを確認して申告や納税が確実に行われているかということを調査す […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
-
- 所属団体
- 東京税理士会
-
- 著書
- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
-
- 経歴
-
大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
事務所概要
Office Overview